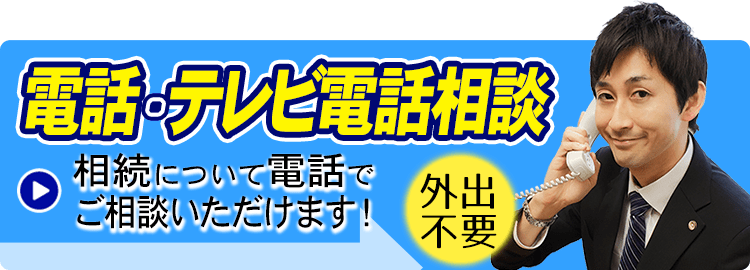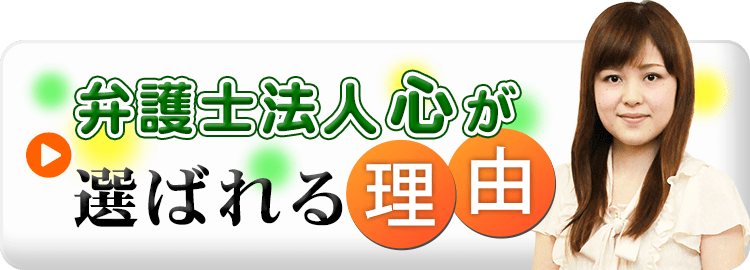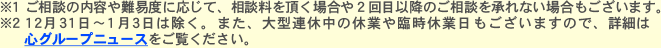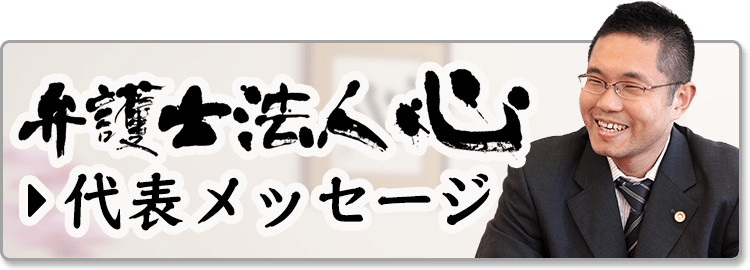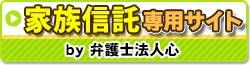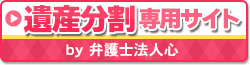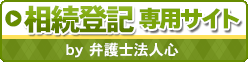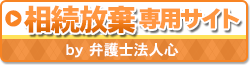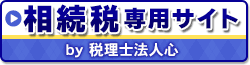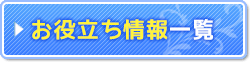相続の特別受益についてのQ&A
特別受益とは何なのでしょうか?
民法では、ある相続人が、被相続人から、生計の基礎となる贈与を受けていた場合には、その相続人については、特別受益の持戻しがなされ、その相続人の相続分から差し引くこととなっています。
つまり、ある相続人が、被相続人から多額の贈与を受けていた場合には、その相続人の相続による法律上の取得分が減額されることとなっています。
これは、被相続人から多額の生前贈与を受けた相続人については、その分、相続による法律上の取得分を減額し、相続人間の公平を図るべきであるとの考えによるものです。
どのようなものが特別受益になるのでしょうか?
民法では、生計の基礎となる贈与が特別受益に該当すると定められています。
基本的には、相続人に対する多額の贈与が特別受益として扱われますが、少額の贈与については特別受益としては考慮されないと考えられています。
たとえば、特定の相続人に対して何百万円もの贈与がなされた場合には、特別受益として考慮される傾向にありますが、少額の生活費の不足分の援助程度であれば、特別受益としては考慮されない傾向にあります。
もっとも、1回あたりが少額の援助であっても、少額の援助が繰り返され、結果的に多額の援助がなされている場合には、特別受益として考慮される可能性があります。
特別受益が存在する場合は、相続分はどのように計算されるのでしょうか?
以下の例で説明したいと思います。
・相続人は子A、子B、子Cの3名
・相続財産の総額は5000万円
・子Aに対して、1000万円の贈与がなされた
上記の場合、各自の相続分は、以下のとおり計算されます。
・子A (5000万円+1000万円)×1/3-1000万円=1000万円
・子B (5000万円+1000万円)×1/3=2000万円
・子C (5000万円+1000万円)×1/3=2000万円
このように、多額の贈与を受けた子Aの相続分は、その他の相続人と比較して、減額計算されることとなります。。
相続分以上の特別受益がある場合は、どうなるのでしょうか?
次の例を考えたいと思います。
・相続人は子A、子B、子Cの3名
・相続財産の総額は5000万円
・子Aに対して、4000万円の贈与がなされた
この場合、子Aの相続分は、以下のとおり計算されます。
・子A (5000万円+4000万円)×1/3-4000万円=-1000万円
このように、特別受益が多額であり、ある相続人の相続分が計算上0円以下になることを、超過特別受益と言います。
この場合、子Aの相続分は存在しないものと扱われます。
他方、子Aは、-1000万円の超過分について、相続財産への返還をしなければならないわけではありません(ただし、子Aに対する贈与がかなり高額でしたら、子Aに対する遺留分侵害額請求の問題が生じることがあります)。
結果として、5000万円の相続財産を、子Bと子Cが2分の1ずつの割合で取得するとの計算がなされることとなります。
何年前までの贈与が特別受益として考慮されるのでしょうか?
法的には、何年前の贈与であっても、特別受益として考慮されることとなっています。
相続税との関係では、考慮される贈与は相続開始前数年以内になされた贈与に限定されていますが、相続分の計算との関係では、このような期間制限は存在しないこととなっています。
特別受益が存在する場合は、必ず持戻し計算がなされるのでしょうか?
ある相続人に特別受益があったとしても、被相続人が、生前、その特別受益について持戻しを免除するとの意思表示を行っていた場合には、持戻し計算はなされないこととなっています。
長年親の介護をしてきたのですが、相続で寄与分は認められますか? Q&Aトップへ戻る