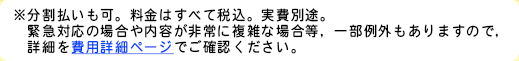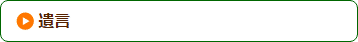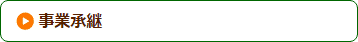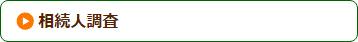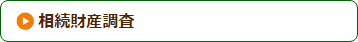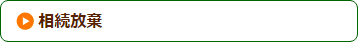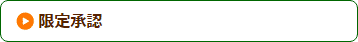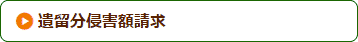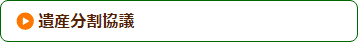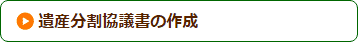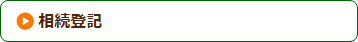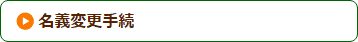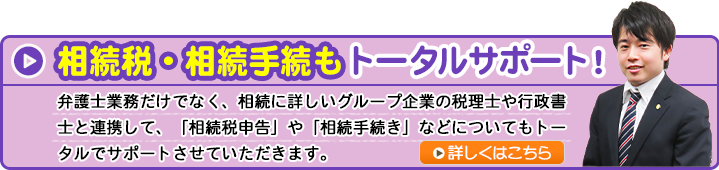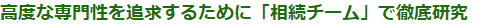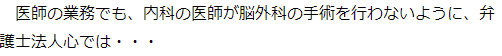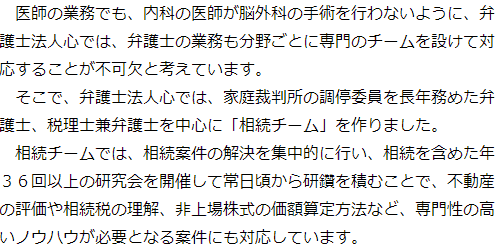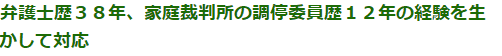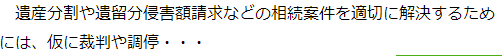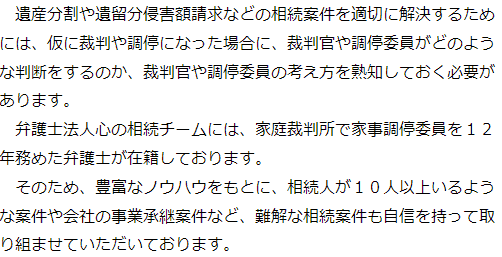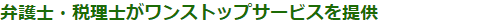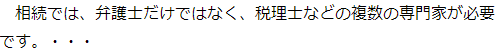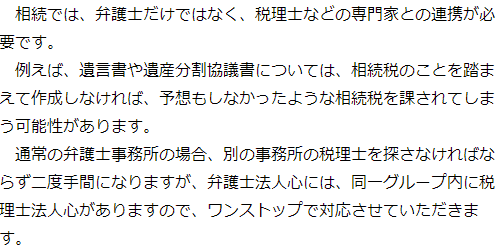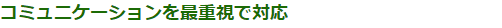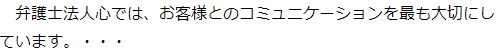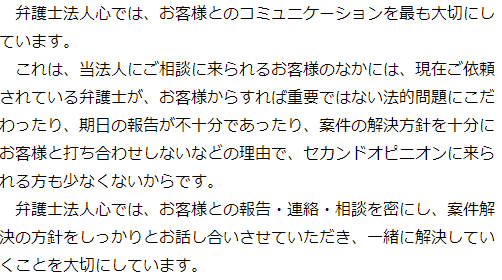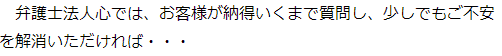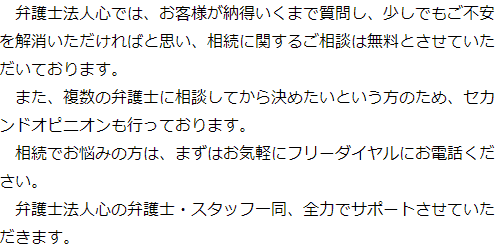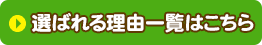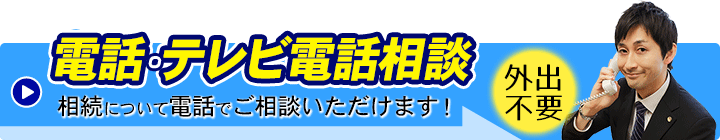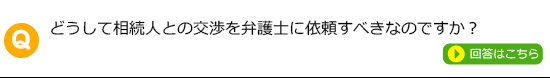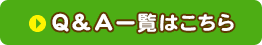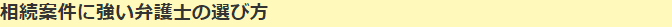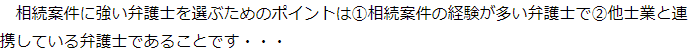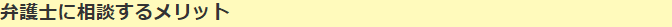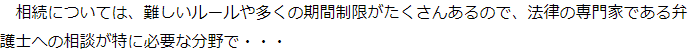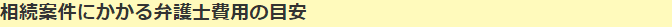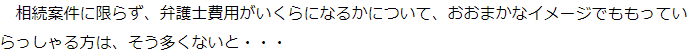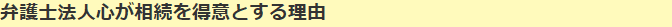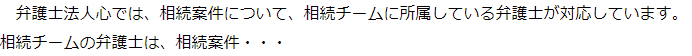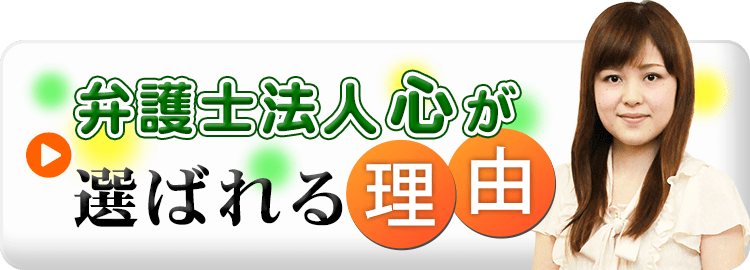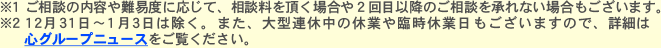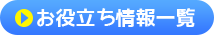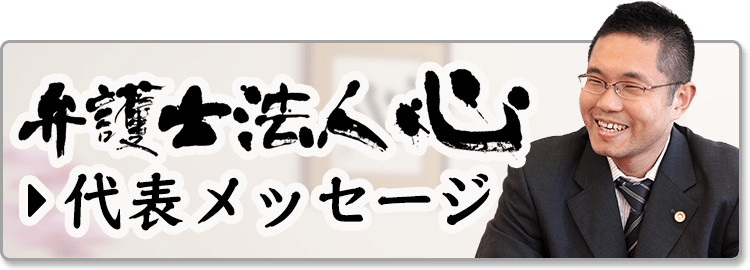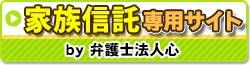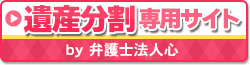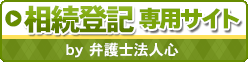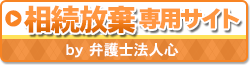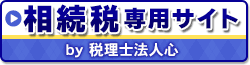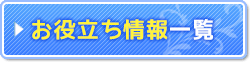松阪にお住まいの方へ
松阪の事務所は、駅から近くアクセスの良い立地にあります。近くに駐車場もございますので、お車でのお越しも可能です。詳細な所在地はこちらからご確認ください。
松阪駅から弁護士法人心 松阪法律事務所へのアクセスについて
1 南口へ向かいます
JR・近鉄のどちらでお越しいただいた場合も、まずは南口(南出口)へ向かってください。

2 南口から外へ出ます
連絡通路を通ってきた方は、階段を降りた先の左側に改札があります。
JRで1番線から電車を降りた方は、降りたホームにある改札が南口の改札(JR側改札)となります。

3 駅を出たらまっすぐ進みます
駅を出たら、タクシー乗り場を右手にまっすぐお進みください。
横断歩道がありますので、そちらも直進して渡ってください。

4 右手側の横断歩道を渡ります
横断歩道を直進したら、すぐ右手にまた横断歩道がありますので、そちらを渡ってください。
目の前に見える101ビルの4階に弁護士法人心 松阪法律事務所があります。
エレベーターで4階までお越しください。


相続問題について弁護士に依頼した方が良いケース
1 法律問題の検討の必要性が大きい場合

相続問題では、相続人同士で意見調整が望める場合と、そうではない場合があります。
相続人同士で意見調整が望めない場合の代表例が、法律問題の検討の必要性が大きい場合です。
たとえば、法律問題について、どのような判断を行うかにより、各自の相続分が大きく異なってくることがあります。
相続人に対する贈与を考慮するかどうか(特別受益の問題)、相続人が被相続人の療養看護等に貢献したことを考慮するかどうか(寄与分の問題)は、その代表例であると言えます。
これらの法的問題について、法律、過去の裁判例等に基づき、適切に判断し、相続分額の算定を行うには、法律の専門家の関与が必要でしょう。
当事者間での話し合いでは、法的問題については、各自にとって都合の良い情報に基づいて主張がなされることがありがちであり、法的に適切な結論を導くことが期待できない場合も多いです。
また、弁護士以外の専門家は、法律の専門家ではないため、法的問題について、厳密な意味で適切な回答を行うことができないことがあります。
このように、法律問題の検討の必要性が大きい場合は、弁護士に依頼した方が良いと考えられます。
2 相続人間の意見対立が強い場合
相続人間の意見対立が大きい場合も、相続人同士での意見調整が望めないところです。
このような場合には、第三者による意見調整や、家庭裁判所の手続の利用が必要になってくることがあります。
このような場面で第三者として意見調整を行うことができるのは、交渉案件を多く取り扱っている弁護士ならではの役割でしょう。
また、家庭裁判所の手続が必要になった場面では、弁護士のみが代理人として行動し、調停や審判期日に出席することもできます。
弁護士以外の専門家は、普段から交渉案件を多く取り扱っているわけではありませんし、家庭裁判所の手続が必要になった場合には、代理人として活動できるわけではありません。
このように、相続人間の意見対立が強い場合も、弁護士に依頼した方が良いと考えられます。
相続の相談から解決までにかかる時間
1 相談から解決までにかかる時間は案件によって異なる

相談の相談から解決までにかかる時間は、案件によって異なります。
お困りごとは早く解決するに越したことはありませんが、現実には、解決までの時間が長期化する案件もあります。
ここでは、解決までの時間の長短に影響する事情を紹介しつつ、それぞれの場合に解決までにどれくらいの時間がかかるかについて、説明したいと思います。
2 遺産分割の仕方について争いのない案件
まず、遺産分割の仕方について争いがあるかどうかは重要な要素です。
遺産分割の仕方について争いがなければ、基本的には、払戻や名義変更の手続を行うことにより、解決に至ることができます。
特段の事情がなければ、不動産の名義変更は1から2か月で完了しますし、預貯金や有価証券の払戻は2から3か月で完了すると思います。
ただ、相続関係が複雑である場合は、必要な戸籍を取得するのに時間がかかります。
戸籍の取得だけで2から3か月の期間を要する案件もあります。
また、不動産を売却して、売却代金を分配するような案件については、不動産の買い手が見つかるまでは、解決することはできません。
不動産によっては、わずかな期間で買い手が見つかることもありますが、何年もかけて買い手を探さなければならない不動産もあります。
3 遺産分割の仕方について争いのある案件
遺産分割の仕方について争いのある案件については、まず、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。
このような意見調整のために、さらなる時間が必要になってきます。
意見調整が早期にできる案件もありますが、特別受益や寄与分の有無等、遺産分割の仕方に影響する事情について、相続人ごとに認識の違いがある案件、感情的な対立が激しい案件については、長期化する傾向にあります。
このような案件については、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判による解決を図らなければならないこともあります。
家庭裁判所の手続を用いた場合は、2から3か月で解決することもありますが、解決まで何年もかかることもあります。
4 他の相続人の意見が確認できない案件
他の相続人の意見が確認できない案件についても、注意が必要です。
たとえば、他の相続人に手紙を送る等しても、他の相続人からまったく返答がないことがあります。
遺産分割は、基本的には、すべての相続人の合意に基づいて行う必要があります。
このため、どのような案件であっても、他の相続人の意見が確認できない限り、案件を解決することはできないこととなります。
他の相続人の意見が確認できない場合は、どのようにして解決することとなるのでしょうか?
他の相続人の住所が判明しており、他の相続人が意思表示が可能である場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判の手続を用いる必要があります。
現在の法律では、他の相続人との合意ができない場合には、家庭裁判所の手続によってのみ、遺産分割を成立させることができることとなっているからです。
遺産分割調停や遺産分割審判の手続については、先述のとおり、2から3か月で解決することもありますが、調停や審判に移行した途端、他の相続人が意見表明を始め、深刻な意見対立が存在することが
明らかになることもありますので、解決まで何年もかかることもあります。
他の相続人の住所が判明しているものの、他の相続人が意思表示ができない状態であることがあります。
たとえば、他の相続人が重度の認知症に罹患している場合です。
このような場合には、他の相続人に成年後見人を選任してもらい、成年後見人に意思表示をしてもらうこととなります。
ただ、成年後見人を選任するためには、家庭裁判所の手続をとる必要があります。
家庭裁判所で成年後見人の選任申立を行い、成年後見人が選任されるまで、少なくとも2から3か月の時間が必要になります。
5 他の相続人の住所が確認できない案件
この場合は、他の相続人に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人に意思表示をしてもらうこととなります。
不在者財産管理人を選任する際にも、家庭裁判所の手続をとる必要があり、選任申立を行い、不在者財産管理人が選任されるまで、少なくとも2から3か月の時間が必要になります。
相続に強い弁護士に依頼するメリット
1 解決の予測可能性が高まる

相続に強い弁護士に依頼すると、解決の予測可能性が高まります。
相続の案件を多く扱っていると、様々な事例において、どのように法令や実務上のルールが適用されているかについ、多くの情報に触れることとなります。
また、審判、訴訟になる案件も多く取り扱うと、過去の裁判例として、どのようなものが存在するかについても、多くの情報に触れることとなります。
こうした過去の経験の蓄積に基づき、最終的な解決がどのようなものになるかついて、より正確に、より早期に予想を行うことが可能になります。
このように、解決についての予測可能性が高まると、予測を踏まえて、あらかじめどのような対処を行うべきかについて、方針を決めることができることがあります。
たとえば、遺産分割調停において、相続財産である不動産を評価する場合には、固定資産税評価額や相続税評価額、査定額をベースに、当事者間で合意を行ってしまう方法、家庭裁判所が選任する鑑定評価を行う方法が考えられます。
このとき、どのような不動産であれば鑑定評価が値上がりしたり、値下がりしたりするかについて、ある程度予測することができれば、当事者間で合意を行ってしまう方が有利か、鑑定評価を行う方が有利かを予測することができ、鑑定評価を強く求める方針を取るべきか、当事者間で合意してしまう方針を取るべきか、方針を決めることができます。
このように、解決の予測可能性を高め、早期に主張の方針を決めることができる場合がある点は、相続に強い弁護士に依頼するメリットであると言えます。
2 手続に配慮した解決が可能になる
相続について解決に至った場合には、解決内容を文書で明確にする必要があります。
話し合いで解決した場合には遺産分割協議書を作成しますし、遺産分割調停で解決する場合には調停調書を作成します。
この解決時の文書については、その後の相続手続で利用することとなります。
このため、解決時の文書は、当事者間で納得して作成しさえすれば良いものではなく、法務局や金融機関、証券会社での手続に利用できるものを作成する必要があります。
法務局や金融機関、証券会社には、それぞれ、手続上のルールがありますので、それぞれのルールを踏まえて文書を作成しなければ、相続手続を行おうとしたものの、受け付けてもらえないといった事態を招きかねません。
相続に強い弁護士は、相続手続をどのように進めるかについて、より多くの経験をしている可能性が高いです。
このため、どのような文書を作成すれば、法務局や金融機関、証券会社での手続を進めることができるかについて、より多くの知識を有しています。
こうした知識に基づき、手続に配慮した解決を行うことができる点も、相続に強い弁護士に依頼するメリットであると言うことができます。
不動産に強い弁護士に相談すべき理由
1 相続と不動産

相続では、不動産をどのように引き継ぐかが問題となることが多いです。
不動産は、大きな価値がつくことが多い一方、物理的に分割することが困難であることが多いですので、相続人間の利害をどのように調整するかが問題になります。
また、不動産については、相続人の側で名義変更のための書類作成を行う必要があり、手間がかかるという点も争点になることがあります。
このように、不動産については、特に相続人間の利害調整や名義変更といった問題が生じやすいです。
このような問題について、適切に対処するためにも、不動産に強い弁護士に相談することが重要になります。
以下では、相続人間の利害調整や名義変更についての問題を具体的に説明し、不動産に強い弁護士に相談することの重要性を説明したいと思います。
2 相続人間の利害調整
不動産の分割協議をする場合は、特定の相続人が不動産を取得し、その他の相続人に対して代償金を支払うという手法を用いることがあります。
このような手法を用いる場合、前提として、不動産の評価額をどのように計算するかが重要になってきます。
そして、不動産の評価を行うにあたっては、不動産について十分な調査を行い、増額要素や減額要素を漏れなく把握することができるかどうかが勝負になります。
不動産の増額要素や減額要素を見つけられるかどうかは、不動産に強い弁護士かどうかによって大きく変わってきます。
不動産の評価自体は、最終的には、不動産仲介業者や不動産鑑定士に委ねられることも多いですが、交渉等の場で、このような増額要素や減額要素を適時に指摘できるかどうかは、交渉結果を大きく左右することがあります。
3 名義変更
不動産の名義変更にあたっては、法務局に、登記申請書と添付書類一式を提出する必要があります。
これらの書類については、すべて、相続人の側で準備する必要があります。
登記申請書については、定まった記載事項に基づいて作成する必要があります。
登記申請書にわずかな文言の違いがあるだけで、登記申請は受理されません。
また、事情の違いによって、記載事項が異なってくることがあります。
たとえば、数次相続の場合(複数回相続が発生している場合)には、登記申請書にその旨を記載すべき場合があります。
添付書類についても、定まったものをすべて提出する必要があります。
また、事情の違いによって、提出すべき書類が異なってくることもあります。
たとえば、被相続人が住所変更登記を行っていない場合には、過去の戸籍の附票を取得したり、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付した申述書を提出したりすることがあります。
このように、不動産の名義変更には考慮すべき点が多くありますので、どのような登記申請書を作成したり、添付書類を準備したりするかについて、網羅的な情報をもっている弁護士に相談すべきでしょう。
この点からも、不動産に強い弁護士に相談するのが望ましいといえます。
相続税についてお悩みの方へ
1 弁護士と相続税申告・納付

相続税については、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月以内に、申告書を税務署に提出し、納付を行う必要があります。
場合によっては、相手方と深刻な紛争状況になっている一方で、相続税の申告・納付を行わなければならないといったこともあります。
このような案件では、相手方と紛争が続いている中で連絡をとり、相続税の申告・納付の手続きを取らなければならないといったことが起こり得ます。
案件によっては、紛争については一時休戦に近い状態にしておき、相続税の申告・納付の手続きを行う必要が生じることもあります。
それは、相続税については、以下のような特殊な制度がとられているからです。
以下では、弁護士が関与する案件で、相続税申告・納付についてどのような特殊性があるかについて、説明を行いたいと思います。
2 未分割であっても申告・納付を行う必要がある
弁護士が関与している案件の場合、被相続人が亡くなってから10か月の期間内に、遺産分割についての話し合いが完了しないことがあります。
このような場合、遺産分割が完了していないことを理由に、相続税の申告・納付の期間が延長されるかというと、そのようなことはありません。
相続財産が分割されていない場合には、各相続人が、法定相続分に従って財産を取得したとの仮定のもと、仮で相続税の申告・納付を行う必要があります。
このため、相続が完了しておらず、現実には財産を引き継ぐことができていないにもかかわらず、多額の相続税の納付をしなければならないといった事態が生じることも起こり得ます。
このような場合には、相手方と協議を行い、双方同意のもと、相続財産の一部の払戻を行い、相続税の納付を行わなければならないこともあります。
3 相続税の連帯納付義務
相続税は、各相続人に対し、相続によって取得した財産額に応じて課税がなされます。
このような話をすると、自分が相続人となった場合は、自分が取得した財産について課税される相続税を納付すればよいということになりそうです。
しかし、相続税には、連帯納付義務がありますので、他の相続人に課税される相続税についても、連帯して納めなければならないこととなります。
したがって、他の相続人が相続税を納付しない場合は、その相続人に課税された相続税についても、納付する義務を負うこととなります。
このため、相続人全員が納付しない限り、税務署から相続税の納付を求められる可能性があることとなります。
この点を踏まえると、相続人全員が申告・納付を行うまでは、税務署から納付を求められる可能性がありますので、お互いに連絡を取り合い、全員が申告・納付を行ったかどうかをきちんと確認するのが望ましいでしょう。
4 相続税についてお悩みの方へ
このように、相続人間の紛争が顕在化している状況においても、相続税の申告・納付の件については、相続人間で連絡を取り合わなければならない状況が生じる可能性があることとなります。
弁護士が関与する案件で、相続税の申告・納付を行う必要がある場合は、この点に留意する必要があります。
相続で困った場合の相談先
1 相続についての相談先の選び方

弁護士に相談する場面は多くないため、相続の問題が生じた際に、どの弁護士に相談すれば良いか分からないという方は、多くいらっしゃると思います。
どの弁護士に相談するかについて、参考となる情報があると、お役に立つのではないかと思います。
弁護士を選ぶときのポイントは様々ですが、ここでは、相続の問題を相談する弁護士を選ぶ際の判断材料について、いくつかのポイントをまとめたいと思います。
相続については、以下で述べるポイントを踏まえて相談する弁護士を選ぶことをおすすめします。
2 調査能力があること
相続について必要な情報を一番持っている人は、被相続人です。
問題は、当の被相続人がすでに亡くなっていますので、相続人は、多くの場合、断片的情報を手がかりに、調査を行わなければならないということです。
こうした断片的情報に基づいて、どこまでの調査が可能であるかによって、相続について適切な主張を行うことができるかどうかは、大きく異なってきます。
例えば、預貯金通帳の記載からは、様々な事項を読み取ることができます。
証券会社からの入金がある場合は、その証券会社に株式、投資信託等の金融資産が存在する可能性があります。
毎月の定期的な振込がある場合は、その人に土地等の賃貸を行っている可能性があります。
多額の出金が行われている場合は、金融機関に問い合わせると、出金された現金の送金先伝票がペアで保管されており、送金先が判明する可能性もあります。
送金先が特定の相続人であれば、その相続人に特別受益があり、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかを、検討する必要もあるでしょう。
このように、相続では、弁護士が、断片的な情報から、必要な調査を十分に行うことができるかどうかが重要になってきます。
このような調査を尽くすことができて初めて、相続財産について網羅的な主張をしたり、交渉上有利になる事情を可能な限り主張したりすることが可能になるのです。
3 他の専門家と連携することができること
相続の問題には、他の専門家の専門領域が絡んでくることが多いです。
例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、最終的に、不動産の登記を行う必要があります。
このような場合には、司法書士に登記を依頼する必要があるでしょうから、司法書士と連携する必要が生じてきます。
相続税申告をする場合は、税理士に依頼することになります。
このように、相続を担当する弁護士は、他の専門家と連携しなければならない場面が多々あります。
そのような場合にもしっかり対応できる体制を整えているところに相談することが大切です。
弁護士による相続人の調査
1 相続人について調査しなければならないこと

相続の話し合いを行う場合には、相続人全員と、誰がどのような財産を相続するかを相談し、合意することが必要不可欠です。
そのための前提として、相続人全員と連絡を取る必要があります。
全ての相続人を把握できているなら問題ありませんが、連絡を取ることができない相続人がいると、相続について有効な合意を行うことができず、不動産の名義変更や預金の払戻等の相続手続きを進めることができません。
ここで問題となるのが、どのようにして相続人が誰であるかを調査するか、どのようにして相続人がどこに住んでいるかを調査するかです。
相続人が確定しないと、他の相続手続きにも支障が生じてしまいますので、なるべく早く相続人を確定させることが大切です。
こうした相続人の調査については、弁護士に依頼することもできますので、ご自身で調査する手間を省き、スムーズに相続を進められるようにするためにも、弁護士へのご相談をご検討ください。
ここでは、弁護士が相続人を調査するときの流れを説明します。
2 相続人が誰であるかの調査
相続人が誰であるかは、相続人を特定する戸籍を調査します。
弁護士は、ご依頼を受けた事件を進める上で必要がある場合には、相続人を特定する戸籍を取得することができます。
このため、弁護士は、各地の市町村役場とやり取りし、必要な戸籍を一通り取得することにより、相続関係を特定することができます。
3 相続人がどこに住んでいるかの調査
相続人がどこに住んでいるかは、相続人の住民票を取得し、住民票上の住所がどこに置かれているかを確認することで調査します。
住民票ではなく、戸籍の附票を取得することでも調査が可能です。
この場合も、弁護士は、ご依頼を受けた事件の進行上必要がある場合には、相続人の住民票や戸籍の附票を取得できます。
各地の市町村役場とやり取りし、必要な住民票や戸籍の附票を取得することで、相続人がどこに住んでいるかを確認することができます。
なお、しばしば、相続人が住民票上の住所に住んでいないため、住民票や戸籍の附票を取得しても、相続人の現在の住所が特定できないことがあります。
このような場合には、窮余の策として、相続人の住民票上の住所の近隣に住んでいる人に聞き取りを行い、相続人の引っ越し先等を確認する方法もないわけではありません。
しかし、プライバシー等の問題が生じるおそれがありますので、このような方法を用いるかどうかは、慎重に検討する必要があります。
4 弁護士への相続人調査の依頼
以上のとおり、相続人調査を弁護士に依頼することにより、相続人が誰であり、どこに住んでいるかという調査を任せることができます。
相続人が誰であるかが分からないという場合や、連絡が取れない相続人がいて困っているという場合は、弁護士にご相談いただけましたらと思います。
弁護士と各専門家が協力できることの強み
1 弁護士と各専門家との協力の重要性

相続は、弁護士と他の専門家の担当分野が密接に関連する部分が多いです。
しかし、弁護士は、他の専門家の担当分野について、詳しい知識を持っているとは限りません。
このため、弁護士の考えだけで事件処理を進めると、他の専門家から見て不利益な事態が生じてしまうおそれがあります。
このような事態を避けるためには、弁護士が各専門家と連携することが重要です。
以下では、専門家同士の協力が不十分だった例を挙げ、専門家同士の協力の重要性を説明したいと思います。
2 専門家同士の協力が不十分だった例
この事例では、相続税の課税価格を越える相続財産が存在したため、相続税が課税されることとなっていました。
相続人の中に、被相続人の配偶者が含まれていたため、相続財産の分割方法についての合意が成立すれば、配偶者が取得した相続財産について、配偶者の税額軽減を用い、配偶者については非課税とすることができたはずでした。
ところが、相続人同士の意見対立が激しかったため、申告期限までに相続財産の分割方法を合意することができませんでした。
そこで、申告期限の段階で、一旦、未分割での申告を行い、配偶者も含めて申告と納付を行うこととなりました。
このような場合、申告期限の段階では、配偶者の税額軽減を用いることができません。
そのため、3年以内分割見込書も合わせて提出し、将来、相続財産の分割方法の合意が成立してから、配偶者の税額軽減を用いて更正の請求をし、税金の還付を受ける段取りとなりました。
その後、弁護士が他の相続人との協議を行ったものの、協議がまとまらなかったため、家事調停の手続きを経て、相続財産の分割方法の合意が成立することとなりました。
相続登記や預金払戻の手続きが完了し、合意が成立して半年が経過した後、配偶者は、税理士に問い合わせ、配偶者の税額軽減を適用して更正の請求を行いたいと伝えました。
ところが、税理士からは、更正の請求を行うことはできないとの回答が返ってきました。
税理士によると、更正の請求の期限は、合意が成立してから4か月以内であるため、すでに更正の請求の期限が経過してしまっており、更正の請求を行うことはできないとのことでした。
こうした事態を避けるには、弁護士と税理士が連携し、あらかじめ更正の請求の期限についての情報を共有するべきだったといえます。
あるいは、合意成立後間を置かずに、弁護士から税理士に合意が成立したとの連絡を行うことも考えられました。
このような事例から、弁護士と各専門家が協力することの必要性を確認できるかと思います。
3 当法人の体制
遺産分割を巡る紛争案件は弁護士法人心の弁護士が対応し、相続税については税理士法人心の税理士が対応するといった連携体制を整えています。
このように、各専門家と必要に応じて連携して相続問題に対処できる体制となっておりますので、複数の分野の知識が必要な内容でも安心してお任せいただけます。
相続の件でお悩みがありましたら、当法人までご連絡ください。
相続の問題を相談する弁護士の選び方
1 相続について相談する際の弁護士選び

弁護士に相続の件を依頼しなければならない場面では、依頼する弁護士をどのように選ぶかは、迷いどころだと思います。
ここでは、相続の問題について、どの弁護士に依頼するかを選ぶ際のポイントをまとめたいと思います。
2 相続について詳しい知識があるか
相続は、必ずしも定まった法的見解が示されているわけではない部分も多いです。
例えば、特定の相続人に対して贈与がなされている場合には、その贈与を特別受益として扱い、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかどうかを判別する必要があります。
特別受益として扱われる場合は、不動産や非上場株式である場合は、いくらの利益として評価すべきかがさらに問題になります。
そもそも、贈与の事実が争われる可能性がある場合には、どこまで証明できる可能性があるのかを検証する必要があります。
弁護士としては、これらの法的問題については、書面作成や交渉の際に即時に扱える知識になっていることが望まれます。
このような専門知識については、普段相続の問題を取り扱っていないと時間をかけて調べなければならず、いざ書面作成や交渉の場面で、必要な知識を使うことができないという事態が起こりかねません。
3 他の専門家と連携することができるか
相続の問題は、関連する問題が多く、他の専門家の領域にも絡んでくることも多いです。
例えば、相続財産の総額が一定額を超える場合には、相続税が課税される可能性があり、申告が必要になってきます。
事案によっては、税金を各相続人がどのように分担するかも考慮した上で、相続財産の分割の方法を決めるのが適切であることもあります。
このような場合には、税の専門家である税理士と連携して対応する必要が生じることもあり、相続の場面では、弁護士が、他の専門家と連携して行動することが、重要になってきます。
他の専門家の関与が必要になる場合には、弁護士から他の専門家に引継ぎを行うべき場合があるでしょうし、事前に、弁護士から他の専門家に意見を確認した上で、相続人間の合意を成立させるべき場合もあるかと思います。
日頃から相続分野での連携に注力している法律事務所であれば、このような場合においてもスムーズな進行を期待でき、税金の面においても適切な相続を行える可能性が高いです。
4 無料相談もご利用ください
相続の問題については、上記のポイントをふまえて弁護士を選ぶことが大切です。
もっとも、実際に会ってみないとわからないこともあるかと思いますので、無料相談を実施している事務所などに一度相談してみるのもよいかと思います。
当法人への相続のご相談は原則無料ですので、松阪で相続で弁護士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士は何を参考にして相続での不動産の評価を行っているのか
1 不動産の評価方法

相続について話し合いを行う際、不動産が含まれている場合は、不動産の評価が必要となる場合があります。
しかし、その不動産の評価方法をめぐって揉めてしまう場合があります。
不動産の評価方法の代表例としては、固定資産評価額、相続税評価額を挙げることができます。
相続に関する交渉でも、これらをベースに不動産の評価額を算定することはしばしばあります。
以下では、これらの評価方法について、説明を行いたいと思います。
2 固定資産評価額
⑴ 一般的には時価より低い金額になる
固定資産評価額は、市町村が定める「固定資産課税台帳」に記載された各不動産の評価額です。
土地の固定資産評価額は、一般的に、時価よりも低い金額になると言われています。
たとえば、目安として、宅地等については、時価の7割程度であると言われることが多いです。
例外的に、道路に面していない土地、傾斜のある土地等については、買手が現れることが期待できないことから、時価がかなり低廉になります。
また、建物の再建築がほぼ不可能である土地、市街地から離れた場所にある土地等についても、時価が低廉になる傾向があります。
⑵ 時価と固定資産評価額に大きな差が生じる場合もある
これらの土地の固定資産評価額について、時価と乖離した金額が設定されていることが、しばしばあります。
特に建物については、ケースバイケースです。
老朽化した建物については、時価はほぼ0円になりますが、固定資産評価額は一定額以下には減価されない(たとえば、新築価格の2割までしか減価償却がなされないことがあります)ため、固定資産評価額の方が高くなる傾向があります。
他方、リフォームされた建物については、リフォームによる価値の増加が固定資産評価額に反映されていないことがしばしばあり、時価の方が高くなることがあります。
他には、マンションについては、市場価値のあるものの多くは、時価が固定資産評価額をかなり上回ります。
3 相続税評価額
遺産総額が一定額を超えており、相続税申告を行わなければならない場合は、個々の不動産について、相続税評価額が算定されることとなります。
土地の相続税評価額については、概略としては、路線価が定められた地域においては、路線価に地積を乗じたあと、不整形地補正等の修正要素を考慮して算定する方法を用います。
路線価が定められていない地域においては、先述の固定資産評価額に、評価倍率を乗じるとの算定方法を用いることとなります。
建物の相続税評価額については、借家権の対象になっていなければ、先述の固定資産評価額と同額になります。
土地の相続税評価額もまた、一般的に、時価よりも低い金額になると言われています。
相続税評価額については、目安として、宅地等については、時価の8割程度であると言われることが多いです。
例外的に、道路に面していない土地、傾斜のある土地等、建物の再建築がほぼ不可能である土地、市街地から離れた場所にある土地等については、相続税評価額が時価と乖離した高い金額になることがしばしばあることも、固定資産評価額と同様です。
相続に関する様々な情報を紹介します
当サイトでは、相続についてのご不安を少しでも解消していただけるよう様々なお役立ち情報を紹介予定です。ぜひご覧ください。