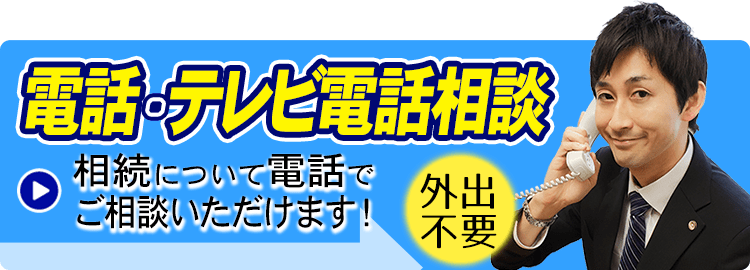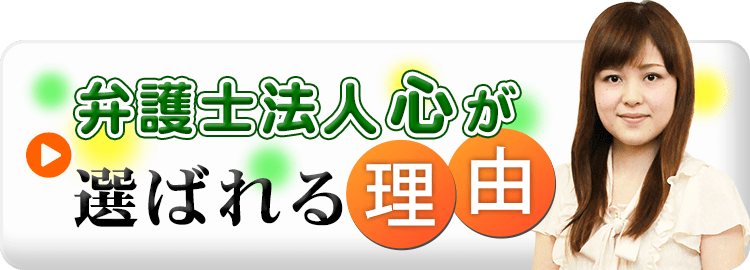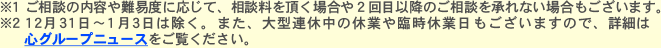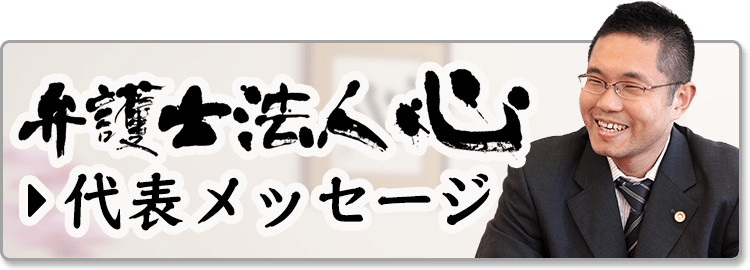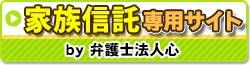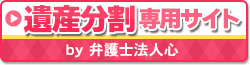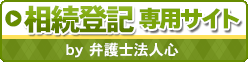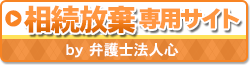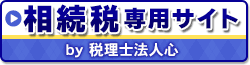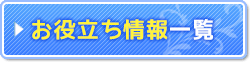長年親の介護をしてきたのですが、相続で寄与分は認められますか?
1 介護について寄与分が認められる場合
結論から言いますと、介護について寄与分が認められることがあります。
ただ、寄与分が認められるケースは想像以上に限定されていますし、認められた場合の金額も限定的であることが多いです。
また、寄与分が認められるかどうかは、個々の裁判官によっても異なってくるのが実情です。
最後に、介護については、家庭内での出来事であることから、これを明確に証明することは難しいことが多いため、寄与分が認められるためには、主張、立証の仕方を工夫することにより、カバーすべき部分が大きいと言うことができます。
以下でそれぞれ詳しく説明したいと思います。
2 寄与分が認められるケース
先例では、介護について寄与分が認められるのは、以下の要件を満たす場合に限られるとされています。
① 被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるものであったこと
まず、介護が被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるものであったことが要件とされています。
たとえば、子が介護を行っていたときは、法的には、子は親に対して扶養義務を負っていると考えられますので、扶養義務の範囲を超えて介護を行った場合に限り、寄与分が認められるとされています。
それでは、介護が通常期待される程度を超えるものであったかどうかは、どのように判断されることとなるのでしょうか?
この点については、具体的にどのような内容の介護を行ったかにより、個別具体的に判断がなされることとなります。
このために、一概に、このような介護を行った場合には寄与分が認められると説明することは、難しいです。
1つの目安として、在宅介護であり、被相続人の介護認定が要介護2以上であったときは、通常期待される程度を超える介護が必要な状態であったと考えられるとは言われています。
もっとも、現実には、介護認定が要介護1以下であったとしても寄与分が認められた事例、介護認定が要介護2以上であったとしても寄与分が認められなかった事例があります。
結局は、介護認定は1つの目安に過ぎず、これだけで寄与分の有無が決まるわけではないことには注意する必要があります。
それでは、被相続人が介護施設に入所していたり、病院に入院していたりした場合については、どうでしょうか?
これらの場合については、寄与分が認められるのは、かなり限られたケースになります。
これらの場合には、普段の身上監護については、基本的には、介護施設や病院の側に委ねられていると考えられるためです。
ただ、相続人による介護が介護施設や病院の要請により行われたものである場合、介護施設や病院の側では対応できない特別の介護行為が必要であり、これを相続人が担っていた場合については、寄与分が認められる可能性が高まると考えられています。
② 無償であったか、無償に近いものであったこと
次に、介護が無償であったか、無償に近いものであったことが要件とされています。
まず、介護について金銭的な対価を受け取った場合については、無償には該当しないため、寄与分が認められないこととなります。
ただ、金銭的な対価が僅かであり、介護負担に到底見合わないものであった場合については、寄与分が認められる可能性があります。
金銭的対価以外にも、以下の事情については、無償であったかどうかの判断で考慮されることがあります。
まず、介護を行った相続人が被相続人名義の家に無償で居住していた場合については、無償居宅が対価と評価され、寄与分が否定されることがあります。
他にも、被相続人から生前贈与を受けていた場合、被相続人が契約していた生命保険金を受け取った場合については、直接の対価関係がなかったとしても、生前贈与や生命保険金が介護負担を補填する側面を有するものであったと評価され、寄与分が否定されることがあります。
他方、これらの利益が、介護負担に到底見合わないものであった場合については、やはり、寄与分が認められる可能性があります。
③ 専従性
介護に従事するため、かなりの負担を要したことも要件とされています。
介護のため仕事を辞めざるを得なかった、収入を減らさざるを得なかった等の事情から、専従性があったとの主張がなされることも多いです。
④ 継続性
数年単位で継続的に介護に従事したことも要件となってきます。
3 個々の裁判官によって寄与分が認められるかどうかは異なる
上記の要件を満たすかどうかについては、明確な基準があるわけではありません。
このため、上記の要件を満たすかどうかは、裁判官によって異なってくるというのが実感です。
この点について、裁判所は全国一律の判断をしているはずとの意見もあるかもしれません。
しかし、現実には、たとえば、介護認定が重かったり、1日の大部分を介護のために使っていたとしても、寄与分が認められなかった例もあれば、介護認定が要支援であったり、1週間のうちの数時間の介護であっても寄与分が認められた例もあります。
これらが一律の基準により判断されているとは到底思えないのが実務側の実感です。
この背景には、裁判官個人の価値判断の違いがあるのではないかと思います。
このため、介護の寄与分が問題となる場合は、個々の裁判官次第であり、一概に寄与分が認められるかどうかは断言できないと言うことができます。
また、主張する側としては、どのような裁判官であっても、できるだけ寄与分が認められる事情を挙げられるよう、最善を尽くす必要があると言うができます。
4 証明が困難であることが多いため、工夫が必要である
介護をどのように行ったかは、第三者でも認識ができるように説明することが困難であることが多いと思います。
その理由は、介護は、自宅内で行われるものであり、第三者の目に触れていない部分が大部分であるからです。
ヘルパーの介護日誌等に、相続人が行った介護の内容が記載されていることもありますが、断片的な記載であることが多く、本当に大変だったことが記載されていない、本当に大変だったことが伝わらないことが多いです。
このため、介護を証明するに当たっては、第三者でも認識できるように、どのように主張、立証の仕方を工夫すれば良いかを検討する必要があると言えます。
まず、断片的な記載であるとしても、できるだけ、介護ついての客観的な記録を取り寄せることが考えられます。
断片的な記載であるとしても、客観的な記録を積み重ねていくことは重要です。
自治体等が保管している認定調査票、主治医意見書、ケアマネージャーが作成した介護計画書、ヘルパーが作成した介護日誌等、客観的な記録を入手することを検討するべきでしょう。
その上で、実際に相続人が行ったことを、どのように生の出来事として伝えるかを検討する必要があります。
1つの方法としては、何月何日に、何時から何時までこのような介護を行った、何月何日に、このような出来事があり、このような対応を行った等の記録を、日記調で作成することが考えられます。
たとえば、例1のような書き方よりも、例2のような書き方の方が、より生の事実として第三者に伝えやすいと言うことができます。
例1
1週間に2回の頻度で、被相続人宅を訪れた。
その際、ケーマネージャーと被相続人の介護の方針について協議した。
例2
1月14日
被相続人宅を訪れた。
被相続人から、庭先で転倒し、近所の医院を受診したという話を聞いた。
ケアマネージャーも、上記の話を把握しており、被相続人の要介護認定の改定の必要があると考えているとのことであった。
このため、1月18日、被相続人宅を訪れ、ケアマネージャーと今後の介護方針について検討を行うこととなった。
1月18日
被相続人宅を訪れた。
ケアマネージャーも被相続人宅に来ており、三者で協議を行った。
私から、先月、インフルエンザに罹患してから、被相続人の日常生活動作が困難になってきており、在宅介護の時間を増やす必要があるのではないかとの話を行った。
この話を踏まえて、ケアマネージャーの方で、要介護認定の改定の手続を行うこととなった。
主治医を受診し、意見書を作成する必要もあるとのことであり、1月25日に受診する予定となった。私も付き添いを行う予定である。
日々の出来事を、継続的に記録したものを作成すれば、本当に大変だったことが、より伝わる可能性が高くなるのではないかと考えられます。
こうした主張、立証の仕方を工夫しなければ、本当に大変だったことが第三者である裁判官に伝わらず、寄与分がまったく認められない事態も生じかねません。
また、裁判官次第ではありますが、本当に大変だったことが伝われば、寄与分が認められる可能性も出てくることとなります。
寄与分については、どのように伝えるかを工夫することが、特に重要であると考えられます。
相続放棄ができない場合はありますか? 相続の特別受益についてのQ&A