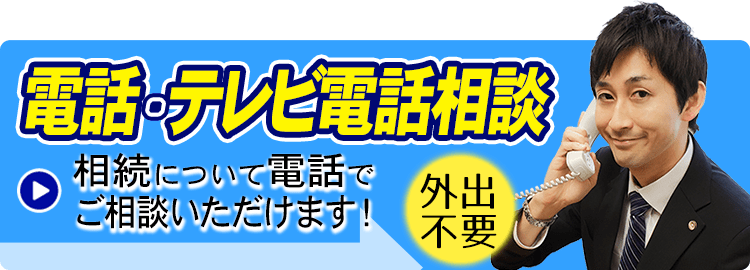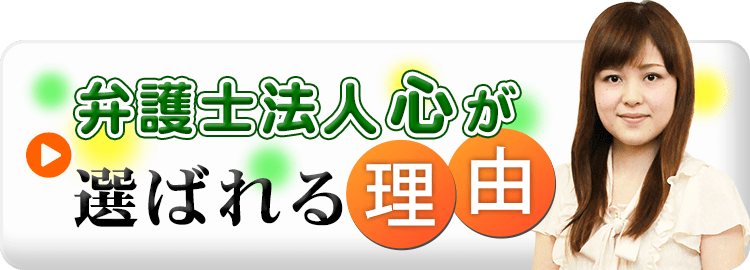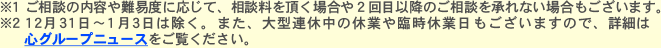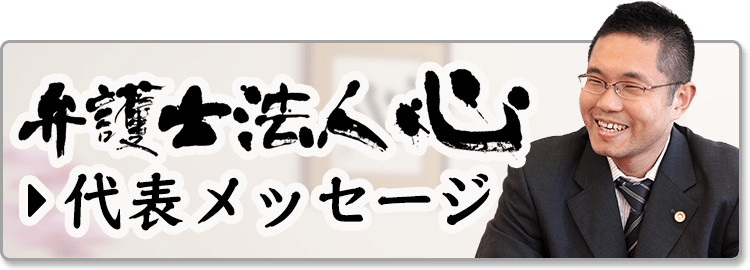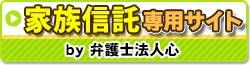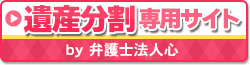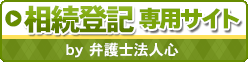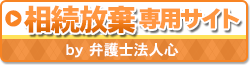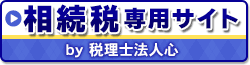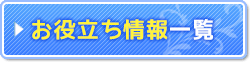遺言書の開封方法
1 遺言書を開封する時は、自分で勝手に開封してはいけません
封筒に入った遺言書を発見した際、自分で封筒の封を解いてしまう方がいます。
しかし、民法上、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない(民法1004条3項)とされており、五万円以下の過料が課せられる(民法1005条)だけでなく、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きをしなければならない(民法1004条1項)とされており、この条文との関係でも問題が起こってしまいます。
以下では、家庭裁判所で適法に遺言書を開封する方法、遺言書が無効になってしまうことを防ぐ方法について解説していきます。
2 開封は家庭裁判所に検認を申し立てる方法で行いましょう
適法に遺言書を開封する方法は、家庭裁判所に対して遺言書の検認を申し立て、検認の手続きが開始してから遺言書の開封を行う方法です。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認するための手続きのことをさします。
家庭裁判所は、検認をすることで、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止することができます。
そして、検認は遺言書の偽造・変造を防止するために、封筒に封印されている遺言書を家庭裁判所外で開封することが禁じられている(民法1004条3項)のです。
そのため、遺言書を保管されている相続人は、検認の期日当日に家庭裁判所内で裁判官の面前まで封筒に封印されている遺言書を持参し、裁判官がこれを開封することとなります。
検認の手続きの詳細は裁判所のHPをご覧ください。
3 検認をしていないことから遺言書が無効となってしまった事例もあります
次に誤って自分で遺言書の開封を行ってしまった場合についてご説明いたします。
まず、原則として、遺言書を家庭裁判所外で開封してしまったとしても遺言書の効力は有効です。
これは、遺言書は遺言者の最後の意思表示であり、可能な限り尊重されるべきと考えられているからです。
しかし、過去には遺言書を裁判所外で開封してしまったために遺言書が無効と判断された事例も存在します。
その事案は、家庭裁判所外で開封した自筆証書遺言に署名・押印が無かったことから、自筆証書遺言に署名・押印がないから民法968条1項に違背しており、遺言書が無効とされた事案です。
この事案では、遺言書の封筒に署名・押印があったことから、封筒の署名押印をもって、自筆証書遺言書の署名押印があったといえるかが問題となりました。
この点について、判旨は「本件封筒には,表に「遺言書」と記載され,裏面に亡太郎の氏名が記載され,「甲野」名下の印影が顕出されており,亡太郎が本件封筒に署名して押印し,かつ,本件文書と本件封筒が一体のものとして作成されたと認めることができるのであれば,本件遺言は,亡太郎の自筆証書遺言として有効なものと認め得る余地がある。」として遺言書が有効になる可能性があることを示しました。
しかし、「本件封筒は既に開封されていたこと(前記前提事実)をも考慮する」と「本件文書と本件封筒が一体のものとして作成されたことを認めるに足りる証拠はない」として、封筒が家庭裁判所外で開封されていたことを考慮して、遺言書と封筒の一体性を否定し、遺言書を無効としました。(H18.10.25東京高等裁判所 平成18年(ネ)第1825号 遺言無効確認請求控訴事件)
この事案からわかるのは、開封前に検認により家庭裁判所内で封筒を開封することで、遺言書と封筒の一体性が認められれば、この事案でも遺言書が有効となる余地があったということです。
そのため、検認手続きの中で遺言書を開封することは重要な要素と言えるでしょう。
4 遺言書を見つけたら弁護士にご相談を
このように、遺言書の開封を行うときには、法律上の手続きを履践することが重要です。
少しでも不安や不明な点があれば弁護士に相談してください。弁護士法人心では、原則無料で電話相談を行っておりますので、お気軽にご質問なさってください。