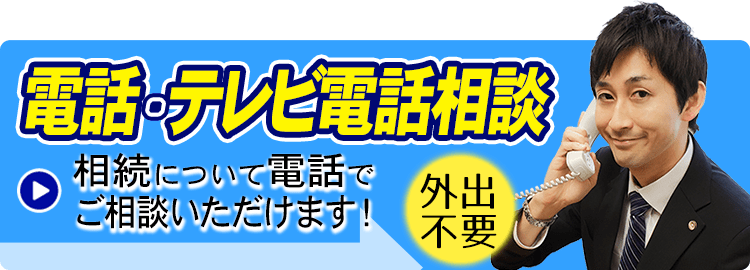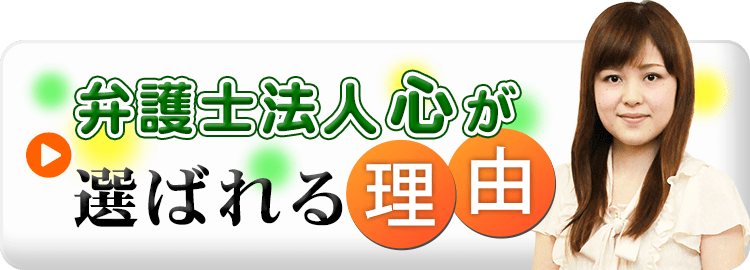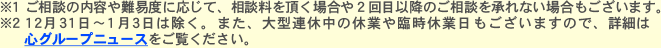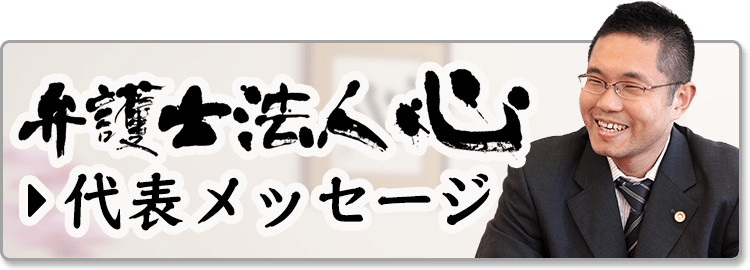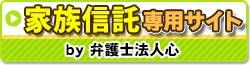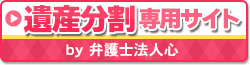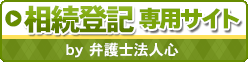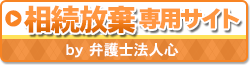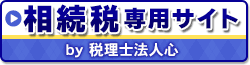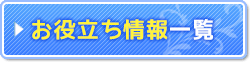寄与分がある場合の遺産分割
1 寄与分とは
寄与分は、被相続人の財産の形成や維持に貢献した相続人がいる場合に、その相続人の相続分を増やす制度のことを言います。
相続分については、民法が親族関係をベースとして、画一的な基準を定めています。
これを法定相続分と言います。
法定相続分に従うと、子が有する相続分は均等になります。
配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者の相続分は2分の1、残りの2分の1を子が均等に分割することとなります。
しかし、現実には、子の相続分が均等になるのは不公平であると考えられるケースがありますし、配偶者の相続分が2分の1で固定とされるのも不公平であると考えられるケースもあります。
このような場合には、寄与分の主張を行い、これが認められれば、相続分が増額修正されることがあります。
このように、寄与分は、画一的な相続分を公平性の点から修正する制度になります。
2 寄与分が認められる場合
それでは、どのような場合であれば、公平性の点から相続分を修正すべきであるとの判断がなされるのでしょうか?
ここでは、いくつかの例を挙げたいと思います。
① 被相続人の財産形成に貢献した場合
被相続人の財産形成に貢献した場合は、寄与分が認められる可能性があります。
たとえば、被相続人に事業活動に貢献した結果、事業収益が発生し、被相続人の財産形成に繋がった場合は、寄与分が認められる可能性があります。ただし、給与等の相当な額の対価を受け取っていた場合は、寄与分が認められない可能性があります。
他にも、被相続人に対して資金的な援助を行った場合は、被相続人の財産、貢献したとして、寄与分が認められる可能性があります。
② 被相続人の療養看護に貢献した場合
被相続人の介護を行っていた等、被相続人の療養看護に貢献した場合も、寄与分が認められる可能性があります。この場合も、被相続人から相当な額の対価を受け取っていたときは、寄与分が認められない可能性があります。
3 寄与分がある場合の遺産分割の方法
① 寄与分の額の計算
最初に、寄与分の額を計算する必要があります。
寄与分の額の計算については、家庭裁判所が判断する場合、比較的、裁判官の裁量が広く認められる傾向にあるため、必ずこのようや計算方法が用いられるという話をすることは難しいです。
このため、ここでは、このような計算方法が用いられる傾向があると考えられるという話はできます。
まず、貢献の結果、被相続人の財産がいくら増加したのかが考慮されます。
被相続人のため、資金的な援助を行った場合は、いくらの資金援助がなされたのかが考慮されます。
親族が介護を行った場合は、これにより民間の介護サービスを利用し、介護事業者への支払を避けることができたと考えられるため、介護事業者を利用したら必要となったであろう費用の分、財産が増加したとの発想が用いられます。このため、介護事業者を利用したら必要となったであろう費用の額が考慮されることとなります。
次に、裁量的割合による調整がなされる可能性あります。
たとえば、貢献により財産が300万円増加したとしても、寄与分としては、そのうちの7割である210万円の限りで認めるといった調整がなされることとなります。
特に、療養看護による貢献については、裁量的割合による調整がなされることが多いです。
これは、親族による貢献は、扶養義務の履行である側面があるため、財産増加分の満額は寄与分としては認定されないためであるとされています。
② 具体的相続分の算定
寄与分を算定しましたら、これを前提として、各自が有している具体的相続分の金額を算定します。
寄与分を有している相続人の具体的相続分の金額の計算方法は以下のとおりです。
(遺産総額−寄与分)✕法定相続分+寄与分
※ 遺産総額については、相続時点の金額で計算します。
4 寄与分がある場合の遺産分割の手続
先述のとおり、遺産分割を行う前提として、寄与分の金額を確定する必要があります。
寄与分の金額については、まずは相続人全員で協議を行い、合意を行うことによって決定するものとされています。
寄与分の金額についての合意が困難である場合は、調停手続により決定することとなります。
調停手続は、家庭裁判所において、調停委員を介して相続人全員が話し合いを行い、調停委員が意見調整を行うことにより、相続人全員の合意を試みる手続のことを言います。
寄与分を定める調停は、単独では調停申立を行うことができず、遺産分割調停申立と同時に寄与分を定める調停申立を行うか、遺産分割調停申立を行ったあとに寄与分を定める調停申立を行わなければならないこととされています。
調停でも相続人全員の意見調整を行うことができなかった場合は、審判手続により寄与分の金額を決定することとなります。
審判手続は、家庭裁判所において、裁判官が当事者全員の意見等を確認した上で、裁判官が寄与分の金額を決定する手続のことを言います。
このように、協議による合意、調停、審判のいずれかにより、寄与分の金額が決定されます。
遺言書の開封方法 多気にお住まいで相続の相談ができる弁護士をお探しの方へ