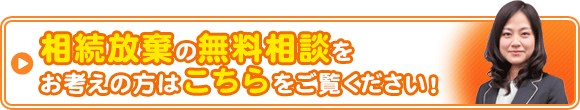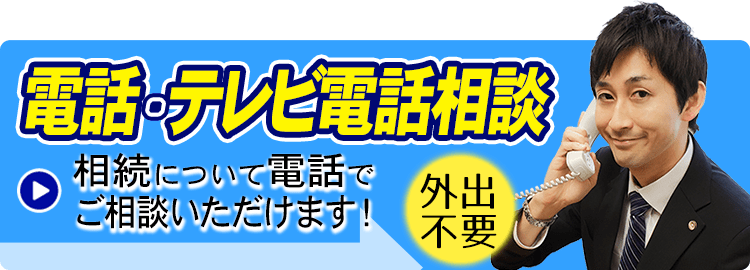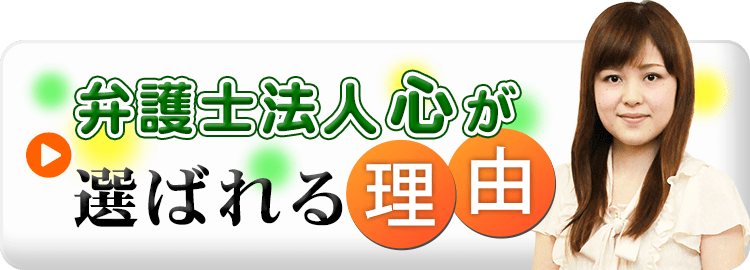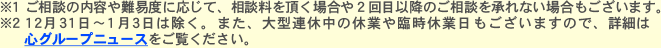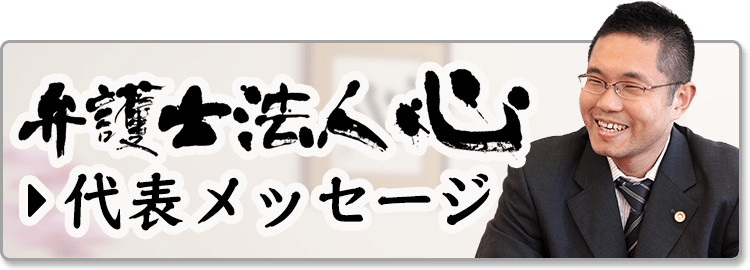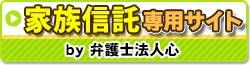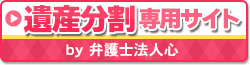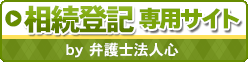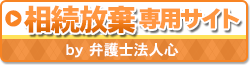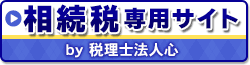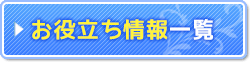相続放棄ができない場合はありますか?
1 相続放棄ができない場合もあります
民法921条では、以下に該当する行為を相続人が行った場合には、遺産を相続することの「承認をしたものとみなす」と規定しています。
- ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- ②相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- ③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(相続の放棄後の背信的行為)
この規定に該当する場合、遺産の相続を単純承認し、相続放棄の選択ができなくなるという効果が発生するのです。
以下は、どういった場合にこの規定に該当するのかという点について説明いたします。
2 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指し、相続財産の売却などの法律行為や家屋の取り壊しなどの事実行為も対象となります。
ただし、遺産を保存するために必要な行為(保存行為)を行っただけでとどまる場合には財産を「処分」した場合に当たらないので、そこの分水嶺が問題となります。
あくまで、「処分」に当たるかは事案ごとに異なる性質のものですので、参考までに以下処分に当たるかが裁判所によって判断された事案についてみていきます。
⑴ 葬儀費用
葬儀費用に関しては、遺産の中から費用を支出すると、原則として「処分」に該当し、相続放棄ができなくなるものと考えられます。
もっとも、葬儀は遺族として当然に行わなければならないものという考え方もあるため、相続財産から支出した葬儀費用が社会的に見て不相当に高額でない限り、「処分」には該当しないとした裁判例が存在します(大阪高決平14.7.3)。
このことから、原則として葬儀費用を遺産から支出することはできませんが、その金額等の諸般の事情を考慮し、例外的に「処分」に該当しない場合があるといえます。
そのため、遺産から葬儀費用を支出したいと考えた際には、弁護士に一度相談することが良いといえます。
⑵ 生命保険金の受取
原則として、被相続人を被保険者として、生命保険契約が締結されていた場合、相続人は相続放棄をするつもりでも、生命保険金を受け取れるとされています。(福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日判決)
なぜなら、生命保険の保険金は、遺産とは独立した相続人固有の財産であると考えられている(最高裁判所第三小法廷昭和40年2月2日判決)ことから、遺産を処分した場合に当たらないからです。
したがって、原則として保険金の受取人は生命保険を受け取っても相続放棄をすることができます。
もっとも、生命保険はその商品の性質によって多種多様であるため、受け取ってよい生命保険か否かは弁護士に確認をとるのが確実です。
⑶ 原則として処分行為に当たるとされる例
「処分行為」に該当するとされる例は、原則として以下のような例となります。
もっとも、当該行為が具体的に「処分行為」に当たる否かは事案によりますので、弁護士に確認を取られるのが確実です。
| 預貯金の解約をすること |
| 債権の取り立て |
| 遺産の譲渡をしたこと |
| 遺産分割協議をしたこと |
| 賃貸借契約の賃貸人たる地位の変更 |
| 経済的価値のある遺品を持ち帰った |
| 不動産の相続登記をした |
| 相続した株式の名義を変更した |
3 相続人が民法915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
民法915条は、相続人が被相続人についての相続が開始したことを知った日から3か月以内に相続放棄をすべき(法律用語で「熟慮期間」と呼びます。)ことを定めています。
つまり、相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に申し立てなければならないといえます。
そして、「相続の開始があったことを知った日」は、例えば被相続人の賃貸の管理会社から、相続人に対して未払い賃料の支払いを求める催告が来る場合等、事実上相続の開始を知った日を指します。
相続放棄の申述等では、被相続人の死亡日から起算して3か月が経過しているが、相続人の「相続の開始があったことを知った日」から3か月以内であることを示すために、賃貸の管理会社からの通知書等を添付して、「相続の開始があったことを知った日」について申述することもあります。
4 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したとき(相続の放棄後の背信的行為)
原則として、相続人は被相続人の遺産を占有している場合、固有の財産に関する注意義務と同程度の注意義務をもって管理しなければなりません。
そして、相続放棄の申述後であっても、相続人は次の相続人や管理者が決定するまで、同程度の注意義務をもって管理しなければなりません。
そのような注意義務を負っている相続人が、例えば相続放棄をした後に高級な服や時計だけを自分の家に持ち帰ってしまうなどしていた場合には、単純承認があったとして、相続放棄が取り消される可能性があります。
この規定は被相続人の財産を悪意をもって隠匿していた場合に対する制裁規定と解されています。
被相続人の「形見」を持ち帰る行為が「隠匿」に当たるかが争われた事案では、相続人が被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯等の経済的価値を有する遺品のほぼ全部を持ち帰った行為は通常想定される形見分けを超える行為であり「隠匿」に該当するとした裁判例があります。(東京地裁平12年3月21日判決)
この裁判例からも分かる通り、例外的に形見分けが許容される場合もありますが、原則として相続放棄をした後の遺産の処分は許容されないため、形見分けをする場合には弁護士に聞くのが良いでしょう。
弁護士法人心はなぜ相続案件が得意なのですか? 長年親の介護をしてきたのですが、相続で寄与分は認められますか?