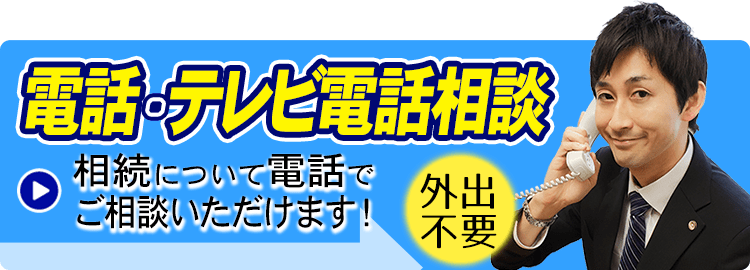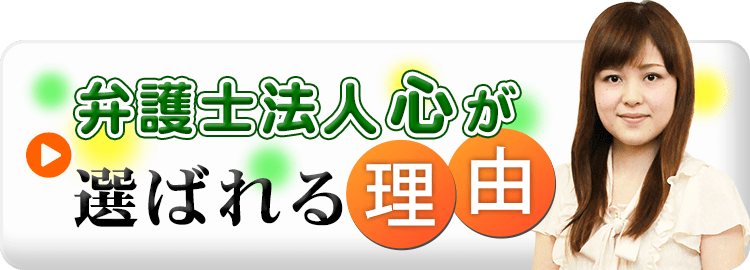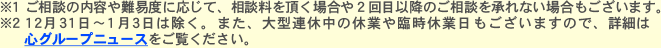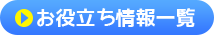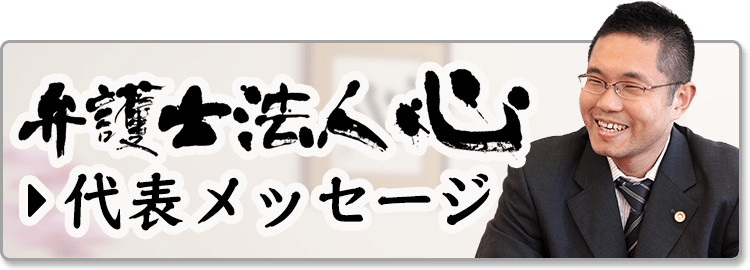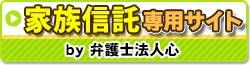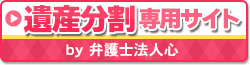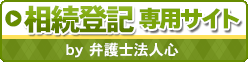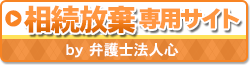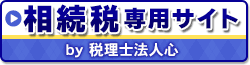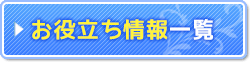相続財産調査
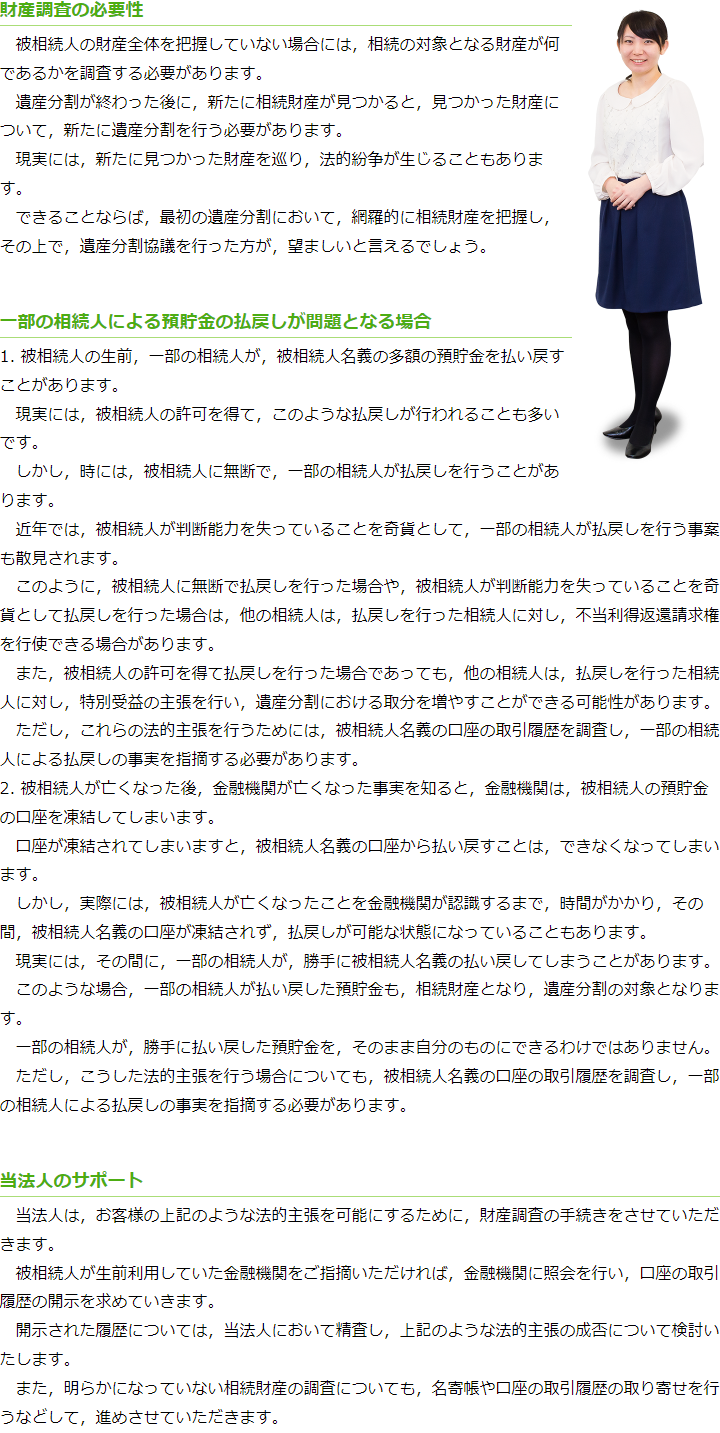
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 定まった手順で調査するのが重要

漏れのない相続財産調査を行うためには、定まった手順で調査を行うのが望ましいと言えます。
調査の手順については、各専門家がそれぞれの工夫を行っているところではありますが、ここでは、不動産について、筆者が用いている調査の手順の一例を紹介したいと思います。
2 不動産調査の手順
① 名寄帳の取得
不動産については、まず、各市町村役場で、名寄帳を取得します。
名寄帳を取得すると、各市町村において所有している不動産の一覧を確認することができます。
相続人の側では、土地や建物が1つだと考えていたとしても、登記や課税台帳上は、複数筆、複数棟に分かれていることがあります。
このような場合には、複数筆、複数棟の土地、建物について、相続手続を行う必要がありますので、名寄帳の記載を確認することが必要であると言えます。
これにより、被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握することができます。
また、名寄帳を取得すると、不動産の固定資産評価額を確認することができます。
不動産の固定資産評価額は、役所が付した評価額であり、必ずしもこの金額がそのまま不動産の時価になるわけではありませんが、不動産の時価の目安にはなり得る指標です。
遺産分割協議の際に、各相続人が取得する財産額を均等にしたいと考える場合には、不動産については、固定資産評価額を参照して、各相続人が取得する財産額を計算することも多いですので、不動産の固定資産評価額についても情報を把握したいところではあります。
なお、不動産を所有している場合は、毎年4月頃に固定資産税の納税通知書が届きます。
固定資産税の納税通知書の課税明細のページを確認すると、被相続人が所有している不動産の一覧を確認することができます。
このため、固定資産税の納税通知書を入手することができる場合は、これを名寄帳の代用とすることもできます。
もっとも、固定資産税の納税通知書には、評価額が低い不動産や、道路やため池等の土地といった、固定資産税の課税対象になっていない不動産については、記載されていないことがあります。
非課税の不動産も含めて慎重に調査を行いたい場合は、やはり、名寄帳を取得し、非課税の不動産も含めた調査を行うこととなります。
② 登記簿の取得
次に、法務局で、登記簿を取得します。
登記簿を取得すると、不動産の法律上の権利関係を確認することができます。
これにより、不動産の法律上の所有者が誰であるかを確認します。
登記簿を調査すると、想定外にも、不動産の所有者が亡くなった先代のままになっていたり、不動産が共有になっていたりすることが判明することがありますので、登記簿の確認も必要不可欠です。
また、登記簿を確認すると、不動産に抵当権や仮登記等の担保権が設定されていることが判明することがあります。
このような場合には、被相続人に債務が残っている可能性がありますし、債務が残っていない場合にも、担保権の抹消登記を行うことができないかを検討することになりますので、やはり登記簿の確認が必要であると言えます。
他にも、地役権や地上権等の用益権が設定されていることがあります。
このような権利が設定されていると、たとえば、高さ15m以上の建物が建築できない等、土地の利用が制限されていることがあります。
土地の利用が制限されていると、将来の土地の利用方法に影響が出ますし、これにより、土地を売却する場合には、売却金額が大きく値下がりする等の影響が出てくることあります。
この点を確認するためにも、登記簿の確認を行いたいところではあります。
③ 公図、地積測量図の取得
法務局では、公図や地積測量図も取得することができます。
公図は、不動産の形状や、近隣土地との位置関係が記載された図面です。
公図は、やや正確性を欠くこともありますが、おおむねの土地の形状等を把握するにあたっては、重要な参考資料になります。
また、公図を確認すると、道路とどのように接しているかについても、おおむね確認することもできます。
土地と道路が接している幅が狭いと、建物を建築することができなかったり、建築できる建物の規模等に制限が生じたりすることがあります。この点も、将来の土地の利用方法に影響しますし、土地を売却する場合の売却金額にも影響しますので、きちんと確認したいところではあります。
土地によっては、地積測量図が作成されていることがあります。
地積測量図は、土地の形状等を正確に測量した図面です。
昭和50年代以前に作成されたものは、正確性を欠くこともありますが、最近作成されたものは、かなりの精度がありますので、地積測量図が作成されている場合は、地積測量図も入手したいところではあります。
④ 住宅地図の取得
公図では、土地の形状等を把握することができるものの、周辺の土地がどのように利用されているか、主要道との位置関係がどうなっているか等については、把握することができません。
言ってみれば、その土地に住んでみたり、その土地を活用してみたりした場合のイメージが掴みづらいです。
周辺の土地が住宅地であるかどうか、さらには近隣に商業施設があるかどうかにより、居住したり活用したりした場合の利便性は異なってくるでしょう。
近隣に主要道があるかどうかにより、移動の際の利便性も異なってくるでしょう。
このような場合には、地図を取得し、周辺の土地の利用状況や主要道との位置関係を把握するのが有益であると考えられます。